とりとめもないコラム
 その⑮
その⑮
重なりのある美しさ
世知辛い世の中になった・・・、とよく言われます。
楽しい話題ばかりであれば良いのですが、世間で耳にする内容と言えば倫理観の欠如に伴う内容や、常識外れの内容、不祥事や疑惑を徹底的に追及する内容など、それにしてもネガティブな内容のものばかりがクローズアップされるなぁ・・・と感じる今日この頃です。
この傾向、いろいろな背景があるのでしょうが、その中の一つとして、デジタル式に物事をはっきりとさせなければ気が済まない、という風潮があるように感じています。
時短で、良し悪しをはっきりさせることは勿論必要ですが、そこにある重なりのあるファジーな部分についても思いを馳せられるようになれば、もっと素敵になるのかも知れません。
例えば、朝と昼の間には朝焼けがあり、昼と夜の間には夕焼けがあり、海水と淡水の混じるところには汽水域があるようにと、重なりがあるからこその良さや美しさがあるように思います。
そのように考えると、今は少なくなりつつありますが、日本家屋によく見られる「縁側」もその一つなのかも知れません。
境界線が曖昧な空間を敢えて設えることで、戸外と屋内との重なりを感じられるようにする工夫がそこにはあったように思います。
縁側に佇むことで感じられる特別な時間は、人の心を豊かにする側面があったのでしょうね。
今回、このようなことを感じたのは、年長さんが七夕の短冊やあじさいの製作で取り組んでいた染め紙作りの姿があったからでした。
絵の具を和紙に滲ませて、その淡い色の重なり具合を心から楽しむ姿を見るにつけ、この活動ならではの尊さを感じるとともに、また一つ子どもたちから教えられたと感じた次第です。
重なりのある美しさを感じることは、人の心を豊かにし、そして人と人との関わりを寛容性ある心地よいものにしてくれるように思っています。

その⑭
1割未満
早いもので、一学期も残り少なくなりました。
さて、表題にあるこの数字ですが、これは、日常的な本園の欠席者数の割合です。
平均すると、どの学級も1割未満となっています。
20人の学級ですと、欠席者が2人未満、ということになります。
これがコンスタントに続いているということが特徴で、これはなかなかできそうでできにくいものであることもお感じいただけるのではないかと思います。
勿論、体調不良の時は迷うことなく欠席することが必要になりますが、欠席が少ないことにより、結果的に日々の取組内容に積み重ねが生まれるようになります。
生活習慣しかり、人間関係しかり、遊びの経験しかり、です。
これらの積み重ねがあることで、経験が深まり、また、広がりも出てくるようになります。
大きな行事も、各種取組の過程を経た上で経験できますので、望ましい形で当日を迎えることができます。
日々の健康管理は、「言うは易く、行うは難し」そのものといった内容なのですが、このことを各ご家庭で継続して取り組まれてきているのは、さぞかし大変な面もあるのでは、と思いを馳せつつ、今日も笑顔で子どもたちを迎え入れようと思っています。
暑さが厳しくなり、体調を崩しがちにもなりますが、くれぐれもご無理なさらず、ご自愛ください。

その⑬
大らかな捉えを
以前、とある若夫婦にお会いする機会がありました。
ちょうど女の子の赤ちゃんが生まれて数ヶ月というところで、人見知りすることなくニコニコする様子に、こちらの目尻は下がりっぱなしです。
話をしていたところ、ご主人は長期間の育児休暇を取得されたのだそうで、なるほど関わり方が実に自然体で、奥さまとも阿吽の呼吸で動くことができているように感じられました。
育休を取得するにあたっては、職場で周囲の理解があって、気兼ねする部分も少なく良かったです、とも話されていました。
さて、このような姿がもっと一般化されていくと良いなぁ、と思いつつもう一方で気を付けなければならない、と感じたのは、自分の時の経験や時代背景を不必要に重ね合わせてしまうことです。
それが強くなれば、ついつい
「私の時は男性の育休なんて考えられなかった」
「今の時代は恵まれすぎている」
「今の人たちは良いわよねぇ・・・」
「我が家の旦那は全く何もしてくれなかった(怒)」
といった不満にもつながってしまいます。
そのあたり、自身のアップデートも必要に思います。
もちろん、人それぞれに多かれ少なかれ満たされなかった思いもあるのでしょうが、敢えてそれはさて置いて、前向きに取り組んでいる今の子育て世代を応援したいものですね。
今の世代だからこそ、どれほどまでに大変な内容があるのだろうと相手を慮りつつです。(実際にそう思います)
また、何かと満たされなかった、その時々の内容が今に反映されて条件整備がなされている面もあるわけですので、バトンはじっくりと真っ当に引き継がれているという、おおらかな捉えをすることも大切ですね。

その⑫
さくらんぼの話
先日、山形県の東根市より、さくらんぼを頂戴しました。
唐突に感じられた方もいらっしゃったと思いますので、もう少し詳しくお伝えいたします。
山形県の東根市は、中央区の友好都市です。
さくらんぼの生産量が日本一であり、佐藤錦発祥の地でもあります。中央区が東根市からさくらんぼの苗木を寄贈いただいたのが縁で、平成3年に友好都市を締結し、現在に至っています。
このほかにも、児童交歓会や「ひがしね祭り」への相互参加など幅広い世代にわたる交流が続いています。
区内の幼稚園児には、今回のような形でさくらんぼを、そして秋にはりんごをプレゼントされています。
テレビの全国のニュースにおいて、中央区で行われたさくらんぼの種飛ばし大会の様子が取り上げられることがあるのですが、それはこれらの交流の内容に重なるものです。
「交流」の意義については、折に触れお伝えしているところですが、今回は都市同士の交流です。
なかなか自分たちだけでやろうにもできることではありません。
このことで、子どもたちの経験が更に豊かになりました。本当にありがたいことです。
本来ならば、直接生産者の方々にお礼の気持ちをお伝えしたいところですがそれは叶いませんので、例年同様にお礼の気持ちを手紙に託してお送りいたします。配布された用紙に、お子さんと一緒にありがとうの気持ちをいっぱい込めて作成していただきますよう、お願いいたします。
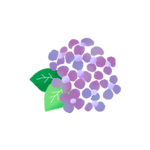
その⑪
一見マイナスに思える時こそ
梅雨の季節となりました。
このように記すだけで、大人は何だかネガティブな思いを抱いてしまいがちです。(私だけなのかも知れませんが…)
例えば、
毎年悩まされる、猛暑の到来が近付く…
戸外で活動できる機会が制限される…
湿度が上がり、不快指数が高まる…
祝日が、ない…(切実)
言い出せはキリがありません。
さて、その一方で、子どもの姿に目を向けてみると、ネガティブよりもポジティブに動いていることに気付かされます。
例えば、雨が降ったとして、子どもにとっては一端「残念!」とはなりますが、時間の経過につれ次第にワクワクドキドキの意外性を伴うアブノーマルな事象との出会いが出てきます。
水たまりができて、子どもが自分なりに関わってみよう、と目をキラキラさせている姿などはまさにそのものです。心が揺さぶられ能動的に関わろうとする姿が次々と生まれてきます。
一方で、子どもたちのこのような姿は、大人からすると眉をしかめるような内容(服が濡れる、汚れる等)であることも多いのですが、このような時こそ、敢えて子どもの思いに添うようにしていきたいものですね。
できるだけ、その思いを認めて、実現できるようにして…
大人としては、ひと手間かかるようなこともあるとは思いますが子どもの笑顔につながると思えばこそ、柔軟な捉えをしていくように努めたいものです。
そのためにも、大人自身が大らかな心持ちでゆとりをもつこと、そしてやわらかい心持ちでいることを大切にしたいものです。
冒頭で、戸外で活動できる機会が制限されると記しましたが、反面、屋内で落ち着いて取り組める状況も生まれやすくなります。
紫陽花やカタツムリなどの梅雨らしい製作物で壁面が彩られるのは、その一環です。
その他にも、人との関わりが持ちやすくなったり、傘の扱いなどの雨の日ならではの習慣面をつけたりする機会も増えます。
一見マイナスに感じることがある時ほど、そうではない面に意識を向ける必要があるのかも知れませんね。
それがナチュラルにできるようになれば、人に対する見方も同様になっていくようにも感じています。

その⑩
「あんパン」を探求する
大変お恥ずかしい話でもあるのですが、私は幼少期にあんパンを食べる度に「あんパンの中のあんは、どのようにしてこのパン生地の中に入ったのだろうか」という疑問を抱いていました。
「あんを入れるのであれば、どこかに穴があるはず!」と思って細かく観察してその形跡を確かめようとしても見つからず、
「それならば、大人にしか分からない特殊技術があるのでは?」と思い、さすが大人は凄い!と独りごちたりと、あれこれと考える日々でした。
この疑問は私が成長するにつれ、自然な形で解決した訳ですが、ここで思うことがあります。
それは、
「一番私が疑問に感じたその旬の時にどのような経験をしていれば一番身になったのか」ということです。
私の場合は幼少期でしたので、経験としては小麦粉粘土を扱った遊びをふんだんに楽しむことができていれば、その気付きは自ずと生まれていたように思います。
しかしながら、単純に経験をさせていれば良いという訳でもなくそこには子どもの素朴な疑問を真剣に受け止め、共に考え試行錯誤を共に楽しみ、そして子どもが腑に落ちた際には心からそれを喜んでくれる大人の存在が必要に思います。
その経験があることで、次なる行動も意欲的に取り組めることでしょうし、学習や生活面など全てにおいて主体的になるはずです。
幼稚園では、今年度からの研究の取組として「探求」を掲げ、日々研究活動に取り組んでいるところです。
小学校以降の「教科」というある種の学習の枠が決まった中での経験とは異なり、幼稚園における「遊び」という幅の広い学習形態の中では、可変性に富んだ経験が各種できます。
私のように、疑問に感じながらも旬の時が過ぎて今に至っているといったことがないようにしなければなりません。
そのためにも、子どもたちが遊びの中で探求する喜びをたくさん味わえるよう、子どもと一緒に探求し続けていきたいと思いま

その⑨
旅はできれば一筆書きで(後編)
(前回からの続き)
待ちに待った、「HIGH RAIL1375」が入線してきました。
これから乗る予定がある方々のために、敢えて詳細な描写は控えますが、内装といい、椅子の配置といい、親切で丁寧なアテンダントさんといい、全てにおいて乗り手の立場に立って、細やかに考え尽くされた「作品」であると感じました。
そして、何よりもその景色です。
一番高い標高を走る列車というその通り、絶景の連続でした。
途中、最高駅である野辺山(八ヶ岳)でしばらく停車してくれ、改札の外に出られる時間を設けてくれました。
明らかに、空気が違うことを感じる幸せなひととき。
そして、清里を過ぎたあたりから、夕焼けに染まる富士山が表れました。これでもかと言わんばかりの内容続きで、私の濁りきった心は無色透明に浄化されていくのでした。
そして、「もう終わってしまうのか…」と心の中で大泣きしながら終点の小渕沢に到着しました。
小渕沢から東京方面に最短で向かうには、「特急あずさ」を使うのが定番なのですが、息子によるプランは違っていました。
小淵沢から中央本線に乗り、高尾で下車。そこから中央線の快速に乗る内容になっていたのです。
ちょうどその頃、中央線にグリーン車両が導入された直後ということでグリーン料金が無料という期間になっており、もう二度とは訪れないその時を楽しむように、という「時間よりも経験」を重視した旅好きならではのチョイスでした。
経験の分だけ時間はかかり、帰宅したのはまさにその日が終わろうとする頃でしたが、おかげさまで心も体(!)もこれ以上はない経験をさせてもらえた一日となりました。
大きな大きな一筆書きの旅となりました。
息子へのお土産は、「HIGH RAIL1375」車内限定の缶バッジ付きクッキーを購入しました。
年齢的にどれだけ刺さるかは分かりませんでしたが、そこは彼が一番思い入れを持っていたこともあってか、「おおっ!」と驚く様を見て、父としては何だかうれしくなったのでした。
この旅、相当オススメです!
しかし、お子さん連れですと日帰りでは非常にハードになりますので、どこかで一泊することを推奨いたします。
時間にゆとりがあれば、是非!

その⑧
旅はできれば一筆書きで(中編)
その旅の行程は、全て細かくプランニングされていました。
「時刻表見るの、苦手だろうけど…」と私用に渡された紙には、彼の直筆でその日の電車の時刻表が細かく記されていました。
そして、彼は追い打ちをかけるように、「妙なタイミングでトイレに行ったら終わりだから」と言うのです。
と言いますのも、これまでに二人で「細かすぎる旅」をしているその時に限って私のお腹が過活動してしまい、トイレへ行くことで変更を余儀なくさせることが多々あったため、これまでと同じ感覚では大変なことになるよ、と警告を発してくれたのでした。
こればかりは努力でどうなるものでもなかろうに、とは思いつつ素直に話を聞きながら、そのプランを凝視しました。
確かに、都心から離れれば離れるほど、電車の本数に限りが出るため、乗り換えを一つ間違えれば大変なことになりそうです。
しかし、今回は、行程通りに進まなければならない目玉な理由がありました。
それは、「天空に一番近い列車」と言われる「HIGH RAIL1375」の座席予約がなされていたからでした。
「HIGH RAIL1375」は、小諸⇔小渕沢を運行するJR東日本の観光列車です。
私も勉強不足で、今回初めてこの列車の存在を知ったのですが、何でも2017年から運行された観光列車で、「HIGH RAIL」は、標高の高い駅・線路を指し、「1375」は、清里―野辺山駅間にある標高(普通鉄道最高地点!)を指しています。
更には、「HIGH RAIL」と「入れる」とをかけて、受験シーズンには受験校に入れるよう、「入れる神社」を設置する駅もあるそうで、プレミア感満載です。
時期や本数が限定されていることもあり、なかなか予約がとれず今回ようやく予約ができたという経緯もあって、息子としては絶対に乗ってほしいという思いがあったのでした。
鉄道の何たるかを分からない私が、このような体験をすることに対して罪悪感めいた思いを抱きつつ、指示通りに早朝の電車に乗りJR高崎線とJR信越本線を乗り継いで、赤羽から横川まで向かいました。
横川で下車。
横川と言えば、あの「峠の釜めし」で有名です。
今、便利なことに峠の釜めしのおにぎりも販売されているため、体内燃費の悪い私はここぞとばかりしこたまおにぎりを買い込み、次のバスの時間まで横川駅付近の廃線跡地を歩くことにしました。
廃線跡地は、遊歩道として整備されていました。
いろいろな事情があって廃線にしたことは理解しつつも、何だかノスタルジックな思いにならざるを得ませんでした。
この廃線が存続していれば、横川から次の目的地である軽井沢までバスではなく、鉄路で行けていた訳です。
そのあたり、息子に言わせれば、「コスパと乗客数」とのことで、この流れは致し方ないとのこと。
(鉄道好きなので存続一辺倒の発想になるかと思いきや、案外そのあたりは現実的です)
バスの時間となり、軽井沢まで乗車です。
それこそ、リアル「峠越え」で、道はクネクネとしていましたが景色は見事なもので、幸せいっぱいなひとときでした。
軽井沢からは、「しなの鉄道」で小諸まで向かいます。
小諸はとても落ち着いた温かみを感じる雰囲気の町で、いつまでもいたくなるような安心感がありました。
そして私は、もはやしわくちゃになった息子の手書きの工程表に目を通します。
いよいよ、「HIGH RAIL1375」の入線です。(次号へ続く)

その⑦
旅はできれば一筆書きで(前編)
かれこれ通算20年くらいになりますが、息子と二人でよく一緒に旅をします。
息子は、小学校に上がってしばらく経った頃には、時刻表をよく眺めるようになっていました。
そして、いつしか彼のリュックの中には必ずお気に入りのJTB時刻表(彼曰く一番バランスがよいとのこと)が入るようになっていたのでした。
実は、私はこの時刻表というのがどうも苦手で、あの細かすぎる数字やレ点だらけの表がチラチラして見えてしまうような、それでいてどこか大切なところを見落としてしまいそうな気もしてしまい未だ感覚的に馴染めないところがあります。
因みに我が家では、娘が私と同様に時刻表にあまり馴染めない派妻は息子と同様で楽しんでいつまでも見ていられる派です。
このあたり、タイプがあるのかも知れませんね。
さて、息子と旅をする際は、彼が行程を全て考えます。
私は食事所や、宿泊する場合はその場所を考える役と、いつしか役割分担をするようになっています。
行程を考えてもらえるところはありがたいのですが、細かく時刻表を見て楽しめる子だからなのでしょうか、分刻みの乗り換えや、乗車時間が長いというハードな内容であることが特徴です。
彼と諸々のハードな旅をしていて(特に青春18きっぷを使う旅で)、私はあることに気が付きました。
「行きと帰りの路線が違う…!」
何だか、経路が一筆書きのようになっているのです。もちろん、そのことで却って時間がかかる面もあったため、息子に聞いてみたところ、「その分電車に長く乗れるし、景色も楽しめるでしょう」という答えでした。
なるほど、確かにそうすることで、帰り道も新鮮さを継続させることが自ずとできる訳で、「もう旅が終わるのか…」という悲しさを紛らわせることもできそうです。
後日、旅行系YouTuberの方が同じことを仰っている動画を見て、旅好きの人ならではの工夫の一つなのかも、と感じました。
そのような調子で、息子は私と一緒でない時も暇さえあれば一人でフットワーク軽く各方法を駆使して各地を旅しているのですが、とある土曜日の夜に、彼が日帰りで予定していた旅に都合がつかず行けなくなったということで、代わりに私に行ってきてみては、と急遽オファーがありました。
(次回に続く)
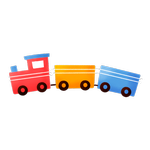
その⑥
「助長抜苗」という言葉
いささかマイナーかも知れませんが、「じょちょうばつびょう」と読む、故事成語です。
読んで字の如く、稲の苗の生長が遅いことが気になるあまり、苗を無理矢理引き上げてしまったために結果枯れてしまった、という故事からきています。
この言葉、子どもと関わる際に自分自身の戒め的に気を付ければならないと思わせるニュアンスがあるように感じています。
「苗が子ども」で、「引き上げる行為が大人からの関わり」に例えます。
子どもが健やかに育ってくれることを願いつつも、どこか大人は期待を募らせてしまう傾向があります。
親ならば当然その傾向はより強まります。
ところが、子どもに対して思い入れが強くなるにつれ、なかなか成長していないように思えてしまい、何とかしたいという気持ちに陥ってしまいがちになります。
それは親心や親切心の賜物ではあるのですが、情が募る関わりをしてしまうあまり、子どもにとって無理を強いてしまい、結果的にマイナスになってしまう、ということにならないよう、気を付ける必要があるように感じます。
本来的に、人間の成長は子どもに限らず行きつ戻りつしながら、緩やかに成されていくものだと思います。
(私の場合は退化の一途を辿る一方なのですが…)
そのように考えると、子どもに対し無理矢理過度過重なノルマを課して、こなせたか否かで評価する、という関わりにも注意が必要に思います。
まだ苗の状態である子どもの根は、繊細で抜けやすい側面があると捉えるに、やはり理想としては大人が適度な水分と太陽のような関わりに努め、子ども自らが根を張ってすくすくと伸びていくような流れを作っていきたいものですね。
簡単にはいかないとは重々承知しつつ…。(苦)
実は、教育の世界でもそのような関わりの大切さが非常に言われています。
「主体的対話的深い学び」、「個別最適な学び」という言葉を耳にされた方も多いかと思いますが、これらは今の内容に重なる考え方です。
特に、柔軟な指導方法・形態がとりやすい幼児教育ではこの内容をより意識していく必要があると考えています。
子育て同様、簡単にはいかないとは重々承知しつつ…。
でも、子どものために頑張らねば、ですね。
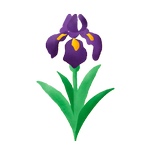
その⑤
「全くどうしようもねぇ父親だなぁ(笑)」
G.W.が終わってしまいました…(涙)。
さて、この言葉、大学3年生の息子に今でも言われます(汗)。
と言いますのも、未だに息子に恨まれていることがありまして…
時を遡るに、凡そ15年前。
息子が小学生になったあたりの頃のG.W.でした。
二人で電車に乗ってお出かけをしようということになり、行き先は、息子が西武ライオンズのファン(今もですが)だったことから西武ドームでした。
西武線を乗り継いで、終点の西武球場前駅に到着です。
野球が開催されていれば良かったのですが、運の悪いことにそうではなかったため、「じゃぁ、ここからどうする?」となりました。
最初にきちんとプランを考えてから出かけなさいよ、という話ですが、経験上、綿密にプランを立てていても、子どもと一緒の時は予定通りにいかなくなるのが常でしたので、あまり考えないようにしていたのです。
通常ならば、ここから西武園ゆうえんちにでも行こうか、というパターンが多いように思いますが、G.W.ならではの混雑ぶりを想像するに、その気持ちにはなれませんでした。
そこで私は、電車好きの息子の気持ちに添おうと、何となく近くに多摩都市モノレールの駅があったことを思い出して(この時点で相当いい加減です…)、そこまで歩いて行こうと息子に提案しました。
案の定、息子は大喜びです。
私もその様子を見て、何だか父親としてのアイデンティティーが満たされた気持ちになり、「何て良い休日なんだ…」と幸せいっぱいになりました。
場所が場所ですので道は限られており、迷うことも少なそう。
喜び勇んで、出発です。
ところが、私は気付いていなかったのです。
距離的にそう遠くないであろうと思っていた多摩都市モノレールの駅「上北台」まで子どもの足で行くのは大変だったことを。
後から分かったのですが、距離にすると3km少々。
途中アップダウンもあり、大人でも結構頑張らなければならないところ、子どもの歩幅で行けば一体どうなるか、という話です。
運動大好きな子どもならばともかく、当時の息子はインドア派、且つぽっちゃり系でしたので、かなりの負荷があったかと…。
途中、私もよろしくない雲行きを感じましたが、途中で引き返す訳にもいかず、結果1時間以上歩いてようやく到着しました。
息子からすると、まさしく表題の言葉でしかないという話だったかと思います。(未だに言われる訳ですので…)
その時、私はある格言を思い出しました。
「とかく男親は自分のペースに子どもを付き合わそうとし、女親は子どものペースに上手に添う」という言葉を。
まさしくその展開そのものでした。
もちろん今はバランスの良い父親ばかりでしょうから、この手の格言はナンセンスであるとは思いつつ、いつまでも息子に言われるようなことのない子育てをしなければと反省した次第でした。
(私の場合、時すでに遅しですが…)

その④
子育てのマニュアルって?
大変便利なことに、世の中は情報で溢れています。
スマホ一台があれば、それだけで欲しいと思った情報にアクセスすることができ、「手軽」に、「便利」に、そして「スピーディー」に情報を得ることができます。
私も百科事典の如くにスマホにお世話になり、その一方で悲しいかな専用の眼鏡も手放せない毎日です(涙)。
保護者の皆様は、きっと子育てに関する各種情報を得るために、活用されていることも多いかと思います。
一方、情報を得るところまでは良いとしても、それをいざ我が子にあてはめようとしたところ、どうもしっくりとこないといった感になることもあるのではないでしょうか。
あくまでも私自身の感覚的な域を出ないところではありますが、人間、特に子どもは個々により個性が大きく出ますので、結果的にマニュアルが通用しない・・・といったことも生じやすくなります。
それではどうすれば良いのでしょうか?
大切かつ一番の近道となるのが、マニュアルは十分に生かしつつ、あくまでも個々に応じた関わりを積み重ねていく、といったことになろうかと思います。
考えてみるに、マニュアル通りにいってしまえば、これほどまでに楽な話はないわけで、逆に考えればそのようになってしまうのであれば、不自然な感じもしてしまいます。
実際のところ、人と人との営みは簡単にいくものではなく、紆余曲折を経ながら紡がれていくものなのではないか、と思います。
それだけに、感じたことをストレートに表現する時期の幼児期の子育ては大変です。(本当に・・・)
ただ、自分自身、幼児期だった頃の我が子と関わったことを振り返ってみるに、確かに手が掛かる側面はありながらも、(全くもって実際には本当にいろいろとありましたよ…)それ以上に感じられる喜びも大きかったように思います。
子どもたちは、毎日精一杯生きているがために、心が右へ左へと大きく揺さぶられます。
その分、親としてはうれしいだけでなく、驚きの姿や悩みにつながるようなこともあるかも知れませんが、一つ一つお子さんとともに喜び、考え、悩みながら歩んでいくことがお子さんの成長にとって一番の近道になるように感じています。
マニュアル通りにいかないところが豊かにあるからこそ、人間の奥深さがあるように思います。
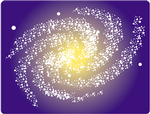
その③
銀河鉄道の父
「銀河鉄道の父」(門井慶喜 著)という作品があります。
映画化もされましたので、ご存知の方も多いかと思います。
このお話、「銀河鉄道の『夜』」ではなく、『父』であることが特徴です。
「銀河鉄道の『夜』」を書いた宮沢賢治氏の『父』、宮沢政次郎氏の視点で、息子をはじめとした家族を描いた作品です。
そこには、息子に対して厳しい父でありたいと思いつつも、実際には情の部分が強く出てしまうことで結果的に甘やかしてしまう・・・といった親心溢れる諸々の姿が描かれています。
人それぞれの感じ方はありますが、私としては、「分かります・・・その気持ち・・・!」と非常に共感する部分がありました。
我が子を思い、そのための親としての立ち振る舞いを考えることは多いと思いますし、実際には試行錯誤の連続といったところかと思います。
とは言え、その一方では、親としての理想には近づけない自分に気付いたり(少なくとも私はそうです)、時には自己嫌悪に陥ったりすることもあるかと思います。
「子育てって、理想通りにいかないんですよ・・・!!」
これが私の本音です。
子どもには、自分とは違う人格があります。
そのため、予期不能なことが次々と起こります。
理屈では分かっていても、次々と生じる理想と現実とのギャップに連日苛まれるのです。
この本を読んで、ちょっと気持ちが楽になるような気がしたのをよく覚えています。
宮沢政次郎氏、過保護で一貫性のない子育てをしている父というように映るかと思いますが、よくよく考察してみますと、我が子にこれ以上ない愛情を注いでいるからこその姿、というのも見て取れるかと思います。
世の中、子育ての正解・不正解はいろいろあるのでしょう。
只、どういう訳か、私はこの親心溢れるお父さんが大好きです。
そして、「過保護に悪い子はいない」という言葉。
これも、密かに好きな言葉です。

その②
「大きな桜の木の下で」
始業式・入園式を経て、初めての週明けとなりました。子どもも大人も、新たなスタートとなりましたので、お疲れになった部分もあったかと思います。
さて、今年は新年度に合わせるタイミングで桜が咲きました。
このところ、4月には散ってしまっていたことが多かったので、新鮮さを覚えつつ、本来はこの時期だったのかなぁ、と思うところでもありました。
偶然だったのかも知れませんが、今年は桜の木の下でランドセルを背負ったり、幼稚園等の制服を身につけたりして思い思いに記念写真を撮っている姿を多く拝見しました。
もちろん私は知り合いでも何でもありませんので、特段話し掛けるようなことはしませんでしたが、何だかその姿はとても素敵で、また微笑ましくもありで、何とも言えない幸せな気持ちにさせられました。
と同時に、ふと我に返り、このような幸せなお子さんをお預かりする立場にあることの重さを改めて感じさせられた次第でした。
幸せいっぱいのお子さんが次の満開の桜を迎える頃、今より比べものにならないくらい大きく成長しているはずです。
その姿を願いつつ、その背中を少しでも後押ししていけるよう、こちらも精一杯努めていきます。
楽しく心地よい日々ばかりではなく、山あり谷ありの一年になるかと思いますが、その分だけ子どもは大きく成長するものです。
皆様とともに歩む一年にしたいと思っていますので、お子さんのうれしいことや気になることなど、遠慮なくお声掛けください。
どうぞよろしくお願いいたします。

その①
ごあいさつ
今年は桜の花が咲いた中での始業式・入園式となりました。
お子様のご進級・ご入園、誠におめでとうございます。
子どもたちと一緒に、楽しく充実した幼稚園生活を作っていけるよう、尽力いたします。
さて、これまで通りの流れにはなりますが、日頃皆様となかなか個別にお話することが叶わないこと等を鑑みて、心に浮かんだ事柄を諸々とりとめもなく書き綴る形で、コラムをお送りいたします。
このことをきっかけに皆様と直接お話をすることができたり、日々子育てで大変な部分での力が少しでも抜けたりすることにつながればうれしく思います。
週一回のペースでお届けする予定でいますので、隙間時間にでもご覧いただければ幸いに存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。




