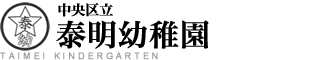5月の子どもたちの様子
★銀座街探検★
今年度はじめて園外へ出る活動である『銀座街探検』に出掛けました。街の歩き方では、何に気を付けて歩けばいいのか、全体に安全指導してから出掛けました。街に2カ所ある交番へ自分たちでつくった鯉のぼりを届けたり、お店のショーウインドウを見させていただき季節を感じたりしてきました。「ここにも鯉のぼりがあるね」「幼稚園に飾ってある兜と少し違う」「おいしそうな匂いがするね」など思い思いに発見したことを言葉にしながら楽しんで探検しました。あいにく途中雨が降ったりやんだりの天候でしたが、傘を差したり閉じたりを自分で行い、頼もしいうめ組でした。




○節句の会○
5月5日の端午の節句を迎えるにあたり、幼稚園で節句の会を行いました。「5月5日は何の日だろう」「街探検で見た『端午の節句』って何?」という疑問を園長先生からのお話で、鯉のぼりをなぜ飾るのかを教員のパネルシアターで知らせました。「子どもたちがみんな元気で居られますようにっておうちに飾る!」「こどもの日なんだね」と、新しく知ったことに対してうれしそうに話す子どもたちの姿がありました。鯉のぼりをつくる前に、兜や菖蒲を飾ったり、校園庭に飾られた鯉のぼりを見て話をしたりしてきたことで、節句の会でのお話が子どもたちの中により入りやすかったと感じました。これからも日本の伝統行事について、一つずつ丁寧に知らせていきます。


◆セーフティ教室◆
築地警察のおまわりさんをお呼びして、交通安全についてと『いかのおすし』(防犯)についてお話していただきました。DVDで分かりやすい内容を見てからのお話しだったこともあり、おまわりさんの呼びかけに「手を上げる!」「右左を見る!」と反応している様子がありました。「どうしてそれをするのか」まで丁寧に教えていただき、「運転手さんに見えるように手を上げよう」とつぶやいている様子もありました。ご家庭でも今一度、交通安全と防犯について、お子さんとお話しいただき、登降園に一緒に確認していただけると、今日のセーフティ教室が生かされると思います。日々気を付けられるように、ご協力よろしくお願いいたします。


●弁当参観・弁当給食試食会●
入園から早1ヶ月が経ち、子どもたちの様子(弁当)を公開しました。弁当の様子を一言で言っても、様々なことがあります。弁当準備も自分たちで頑張って行っている様子から見ていただきました。手の洗い方、うがい、その後コップを置く→椅子・鞄を持ってくる→机の上に必要なモノを出す・・・毎日丁寧にやり方を知らせながら経験が積み重なるようにしてきたことで、「自分でできるんだよ」と自信満々に支度しているように見えました。食べている様子の場面では、「思ったより食べていた」「友達と食べるとこんなに食べるんですね」等感想をいただきました。実際のお子さんの様子を見ていただいたことで、幼稚園のよさが伝わり、うれしく思います。また、おうちの方に弁当給食を実際に食べていただきました。「子どもたちが体験していることを保護者が体験してみる」ことで、さらに幼稚園教育について意義を感じる機会になったのではないでしょうか。6月、7月にも教育活動に参加していただく機会を設けています。是非、どんなことを子どもたちが経験しているのか想像しながらご参加ください。楽しみにしております。

☆日比谷公園散歩☆
セーフティ教室の後に園長先生から「交通安全のこともたくさんわかったし、今度は日比谷公園にみんなで行こうか?」とお話があり、大喜びのうめ組。日比谷公園がどんな場所なのか、写真を見たり、いつ行くのかと指折り数えたりして楽しみにしてきました。当日、お天気にも恵まれ、元気よく日比谷公園に出掛けました。もちろん、セーフティ教室で教えてもらった「運転手さんに見えるように手を上げる」「右左をしっかりみる」を行き帰りの横断歩道で実践している姿がありました。


日比谷公園に入ると、きれいに咲いているお花が迎えてくれました。特に、バラが子どもたちの目の前にあり、見たり匂いを嗅いだりして満喫しました。

泰明幼稚園の子どもたちが大好きな『三笠山』までどんどん歩き、ついに到着!探検バックを持って思い思いに動き出しました。たんぽぽの綿毛を見つけて「ふ~」っとすることを楽しんだり、鳩を見つけて静かに追いかけたり、小さい花を探検バックにたくさん入れたり、頂上の大きな石の上で一休みしたり・・・あっという間に時間はたち、探検バックは子どもたちの発見でいっぱいになりました。三笠山から幼稚園に戻る道中もたくさんの花があったり、大噴水の様子を覗いたり・・・自然を堪能した子どもたちでした。






散歩翌日からは、砂場や園庭遊びの時に、日比谷公園で摘んできた花や葉っぱを材料にしてごちそうつくりを楽しみました。行事で終わるのではなく、その前後を大切にこれからも活動をしていきます。